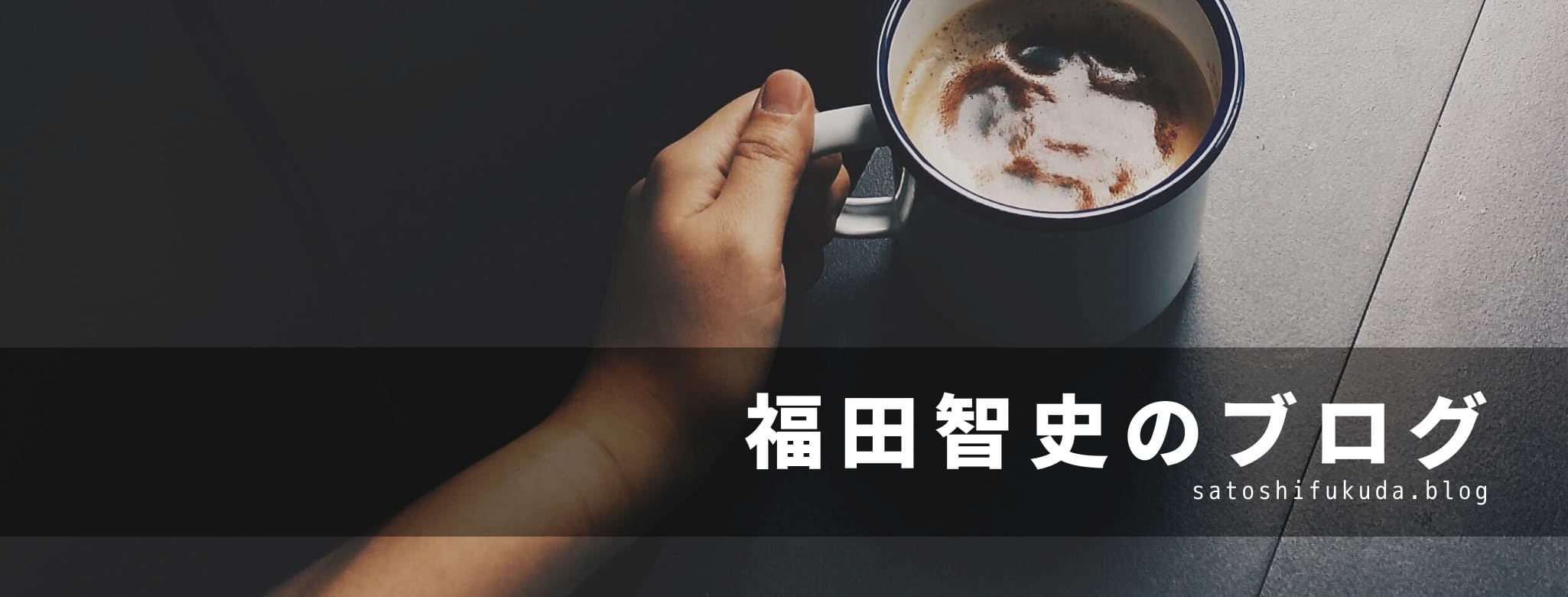「モチベーションを劇的に引き出す究極のメンタルコーチ術」から学ぶ発達障害者のマネジメント
はじめに
数多くのトップアスリートを育てた鈴木颯人氏が書いた「モチベーションを劇的に引き出す究極のメンタルコーチ術」。オリンピックに出場するようなトップアスリートは、一般人には想像もできない努力をしています。テレビの密着やドキュメンタリーでも「どうしたらそこまで自分を追い込めるのか」と思う時があります。
それを支えているのが「モチベーション」。その高次元のモチベーションを引き出し、維持する方法に興味がありました。実際この本を手にとってみたところ共感する部分が多くあったので、発達障害者のマネジメントに役立つヒントを考えてみました。
人は信頼度に応じた会話しかできない
部下のモチベーションを引き出すには「メンバーの気持ちを引き出せる存在になることが重要」と書かれています。そのポイントは「信頼関係の構築」。信頼関係が大事という点に異論はないですが、その構築と維持はなかなか難しいです。
個人的なオススメは定期的な「1 on 1」の実施です。頻度を下げてもいいのでとにかく継続することでマンツーマンのコミュニケーション総量を増やします。家族や恋人、友人関係も同じです。人間関係の密度は一緒に過ごした時間の長さに比例します。

但し、1 on 1 を継続するには一定の「雑談力」と「質問力」が必要です。どんなことに気をつけて話をすればいいかは、この後に出てきます。
あなたを認めているという空気が成果を変える
部下のモチベーションを引き出すには、マズローの欲求5段階でいう「社会的欲求と承認欲求を満たしてあげることが重要」と書かれています。二流のリーダーはすぐに結果を求めるが、一流のリーダーはまず相手を認める。これは、自己肯定感が低い傾向がある社会的マイノリティの方(障害者の方など)と接する上で非常に大事です。
私が代表をしていたグリービジネスオペレーションズ(以下、GBO)では、「MVP表彰制度」という形で「認める」機会を設けていました。MVPは「金銭的ボーナス」ではなく「イベント」です。社員と管理スタッフの投票を参考に「その年に企業ビジョンをもっとも体現した人」を選定し、全社員の前で表彰していました。

一流のリーダーは失敗談を恐れずに語る
部下のモチベーションを引き出すには「自分のことをオープンにする姿勢が重要」と書かれています。本の中では「ジョハリの窓」にある「隠された自己」の開示とも表現されています。成功談をマウンティング気味に話すのではなく、誰にも言ってなかった失敗談をたくさん話すべきなのです。
とはいえ、なんでもかんでも自己開示すればいい訳ではありません。部下の前で唐突に自己開示を始めても違和感しかありません。自己開示のコツは、相手の悩みや失敗に対して共感し、自身の失敗経験を重ねてフィードバックすることです。
1 on 1 の中で「何か困っていることは?」と質問し、仕事でうまくいってないことや、つまずいていることの話しを引き出します。それに対して、組織のリーダーが「同じ経験あるよ」と共感してあげることは、とてつもない安心感につながります。そこに具体的なエピソード(失敗談)を加えてあげればよいのです。
目標を1日の行動に細分化する
部下のモチベーションを引き出すには「目標を行動レベルにまで落とし込むことが重要」と書かれています。ワクワクする壮大な目標を立てたところで、その目標に向かって誰もが自走できるわけではないです。「これならできそう」と思えるレベルまで目標を細分化するのです。
よりわかりやすくするために、発達障害がある子どもの療育でも活用されている「応用行動分析(ABA)」のフレームワークを使ってみます。「モチベーションの低下」を問題行動とした場合、以下のような整理ができます。
- A:先行事象 -> 目標が高い・仕事が難しい等
- B:問題行動 -> モチベーションの低下
- C:後続事象 -> 仕事をしない
ここで、モチベーションの低下を当人の問題とせずにAとBに目を向けると、
- A:先行事象 -> 目標が
高いを1日に行動に細分化する・仕事が難しいのハードルを下げる - B:問題行動 -> モチベーションの
低下維持 - C:後続事象 ->
仕事をしない褒める・認める
一例としてこのような改善が考えられます。本の中では「モチベーションが続かないならハードルを下げよ」とも書かれており、目標の設計がモチベーションマネジメントにおいて重要であることがわかります。前述の「あなたを認めているという空気」づくりはCで生きてきますね。
応用行動分析とは…従来の心理学では、行動を起こす理由をその人自体、つまり個人に求めていたのに対し、行動分析学では、人の行動や心の動きは、個人とそれを囲む環境との相互作用によって生じると考えました。つまり、その人の気持ちや行動の原因を、周囲の環境との関係のなかで見ながら考えましょうというものです。 – 引用元(発達障害の療育のベース「応用行動分析学(ABA)」とは?)
さいごに
人工知能(AI)が人間の知能を超えつつあります。ただ、AIになくて人間にあるものが「モチベーション」です。「モチベーション」は、下がると急激な生産性の低下を生む一方で、上がれば期待以上の力を生む源泉になります。モチベーションマネジメントは「諸刃の剣」ではありますが、組織を牽引するリーダーにとっては軽視することのできない必須スキルなんです。