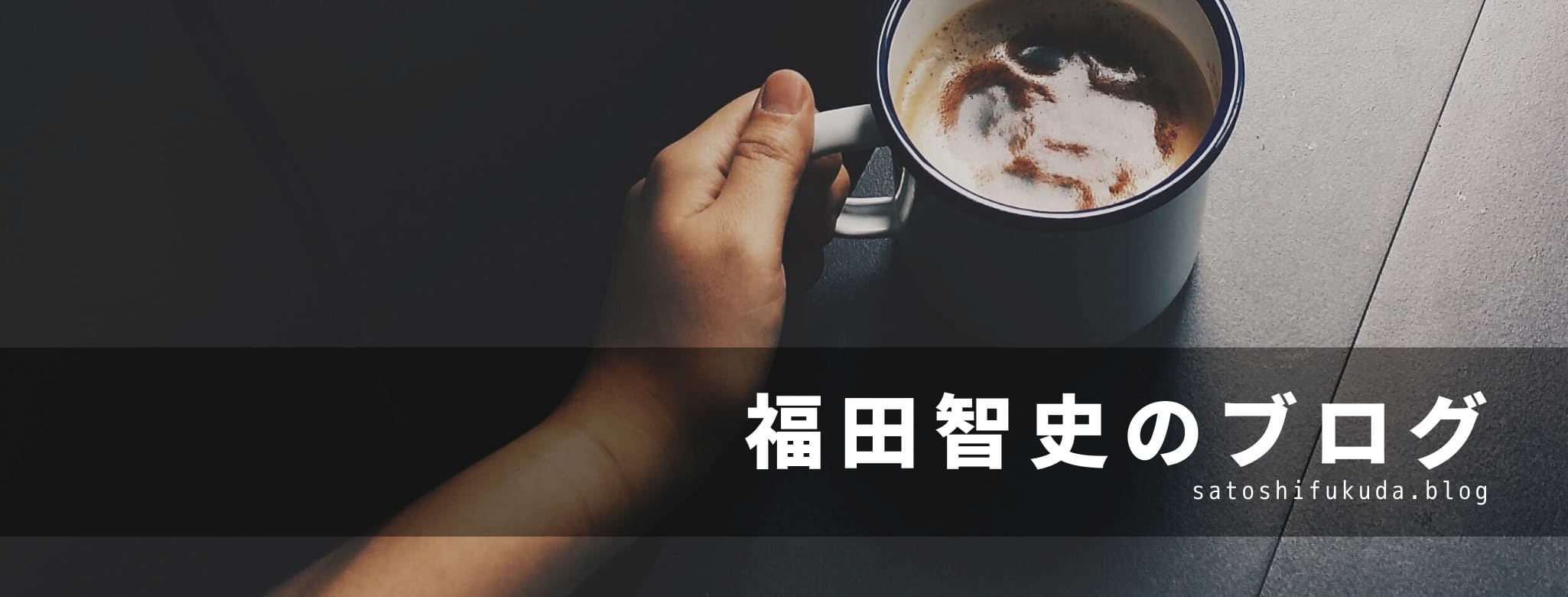eスポーツを活用した障害者雇用マネジメントの可能性
はじめに
5月31日、「障害者雇用」と「eスポーツ」のコラボレーションイベント、バリアフリーeスポーツ大会に参加してきました。私自身は「リモートワークと障害者雇用」というテーマのオンラインパネルディスカッションに、特例子会社グリービジネスオペレーションズ(以下、GBO)の社員で構成される有志チームは、その後に行われたゲームマッチに参加しました。

在宅勤務で気づいた「人恋しさ」
コロナ禍の在宅勤務で感じたことがあります。雑談や挨拶、会釈など、日常の自然なコミュニケーションからうまれる「自己肯定感」があるということです。
オンラインであっても、必要なビジネスコミュニケーションはビデオ会議ツールやチャットツールを導入したことである程度は仕組み化できました。その一方で、ビデオやチャットの会話をしているときと、自宅で一人黙々と作業をしているときで「つながり」の落差が激しいことも再認識しました。シンプルに「人恋しく」なります。
もっと極端な言い方をすると「自分のやってることは意味あるんだっけ?」とか「自分の仕事は誰かに必要とされているのかな?」という、今まであまり感じることのなかった心配事まで頭から離れなくなります。特に、ADHD特性を持っていたり、不安障害を抱える社員であればなおさらです。
無意識に生まれていた自己肯定感
同じオフィスにいるだけで感じられていたゆるいつながり。それは「ここにいても良いんだ」という自己肯定感につながっていて、発達障害者のマネジメントに重要だと思いました。
自動販売機で顔を合わせる、お手洗いに立ったときにビルの廊下ですれ違って会釈する、就業後に一緒に駅まで行く、社長や管理スタッフから声をかけられる等。こういった何気ないやり取りには意味があったんです。ちょっとしたコミュニケーションで充電される「自己肯定感」ってすごく大事です。
eスポーツと障害者雇用マネジメント
今の社会情勢ではしばらく在宅勤務が続きそうです。何かしら手を打たないといけない。そう思って始めたのがゲームを通じてゆるくつながることでした。ゲームを一緒にすることは、ビデオやチャットと違い、そのきっかけに業務上の理由が必要ありません。無理に何か発言する必要もない。
まだまだしばらく続きそうな在宅勤務を前提とした働き方において「自然なコミュニケーション」や「ゆるいつながり」を生む方法としてのeスポーツには大きな可能性を感じました。
さいごに
8年前、海外に長期出張をしていたときのことです。当時はまだガラケーでしたが「探検ドリランド」や「怪盗ロワイヤル」といった携帯電話向けのソーシャルゲームで、日本にいる仲間とゆるくつながっている感じがホームシックを和らげ、とても心地よかったのを覚えています。障害者雇用 × eスポーツ は、障害者雇用におけるオンラインマネジメントの一助になるのではないでしょうか。
P.S.
先日、社内の全体ミーティングがあったので、マリオカートとどうぶつの森(共にスマホアプリ版)の自分のフレンドIDを全社員に共有してみました!