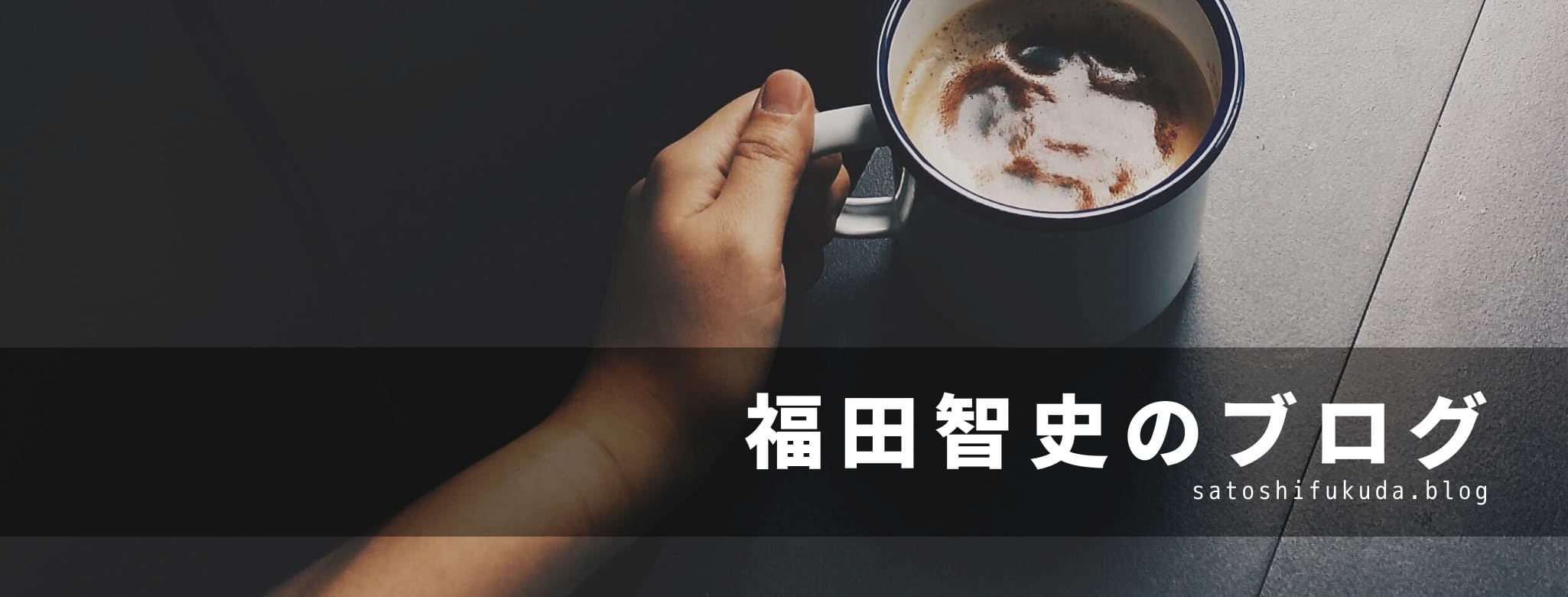発達障害とは?と聞かれたら
はじめに
発達障害とは…と聞かれたら。明文化するのが非常に難しい問いですよね。昔とくらべて「発達障害」そのものの認知は上がってきているので、Googleで検索するだけでもさまざまな情報ソースがでてきます。
発達障害者支援法上の定義
2005年(平成17年)の4月1日施行された「発達障害者支援法」では以下のように定義されています。
発達障害:自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの
今では「大人の発達障害」という言葉があるほど、低年齢者に限った障害ではないのですが、アルファベットの略称で言われるASD(自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群)やADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)などがまさに明文化されてます。
個人的におすすめの情報ソース
基本的にはどの情報ソースも間違ったことは書いてないです。ただ、それを「説明する人」と「受け取る人」によってわかりやすさはさまざまです。ここでは私が個人的におすすめのわかりやすい情報ソースを3つご紹介します。
2分の動画で解説
Twitterにアップされた動画スタジオ「onemedia」の動画。若い人に説明するには非常に使い勝手がいいので、これを見つけたときは思わず「作ってくれてありがとう!」と思いました。特例子会社の代表をやっていたいとき、新卒社員向けの研修で「発達障害」について説明するときは、この動画をつかいました。
私って「コミュ障」なのかな?とか、細かいミスを直せないのは「努力が足りないせい」なのかな?って自分を責めてる人がいるかも。
でも実はそれって診断のつく「障害」の場合もあってサポートも受けられるんだよね(メッセンジャー:レオナ)【個性?障害?👫発達障害っていったい何?|#ONECURIOUS】 pic.twitter.com/772N1fXgrz— ONE MEDIA|ワンメディア (@onemediajp) October 31, 2018
小学4年生の男の子が自分の発達障害について創った資料
小学4年生の当事者の男の子がつくった資料がnoteで紹介されてました。小学生とは思えない表現力と、わかりやすい言葉と構成で説明されています。必見です。
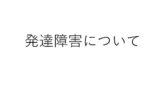
札幌市の発達障害「虎の巻」
漫画イラストなので読みやすいのと、例えとして用いられている「パン作り」。これが障害者雇用の現場だけでなく、教育現場や発達障害児を持つご家庭でも大いに参考になると思いました。
職場編では、虎夫さんのパン作りの例を紹介。先輩から「適当にクリーム塗っといて」と指示されて作業したところ、塗りすぎて注意を受けてしまいます。「クリームをあんなに塗るなんて『普通に考えて』ありえない」という先輩と、「『どれくらい』塗るかおしえてくれなかったのに」と感じている虎夫さん。

個人的におすすめの本
私が、特例子会社の代表に就任した翌年に発売された本「カンタ」。著者はあの「池袋ウエストゲートパーク」 の石田衣良さん。著者のファンだったのですぐ買って読みました。おすすめです。
こちらは2018年発売の本。著者は東田直樹さんで重度の自閉症の当事者です。自閉症やADHDのことが非常にわかりやすいです。「カンタ」もそうですが、読んだら思わず涙がでてきます。
栗原類さんは、NHKの番組で私が代表をしていた特例子会社に取材・見学にきていただきました。また、お母様とはイベントでご一緒させていただいたこともあり非常にご縁があります! 学校の先生や子をもつ親御さんにも読んでほしい一冊です。
さいごに
今回ご紹介したのはほんの一部です。まだまだ紹介したい映画やドラマもあるのですが、今日はここまでにしたいと思います!