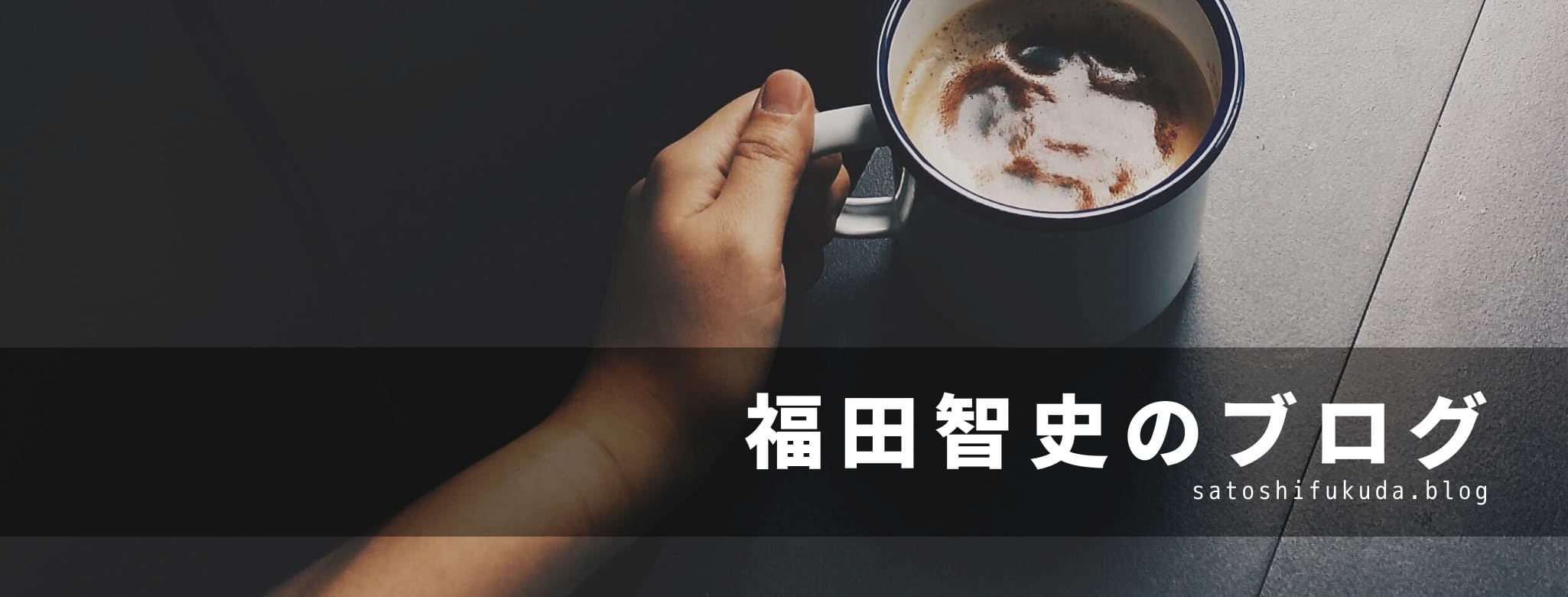障害者雇用のマネジメントにも生きる「適度な無関心」のススメ
はじめに
長時間労働やハラスメント、何かと社会問題化することが多くなった日本の企業の働き方。そこには、発達障害者が働きづらい理由と、障害者雇用のマネジメントにつながるヒントが隠されている気がします。
働きづらさを解消するキーワードは「適度な無関心」
最近は、障害者だけでなく健常者も働きづらさを感じています。その声はSNSを通じて表面化し、モンスター社員と揶揄されることもあります。解決策についてはさまざまな議論がありますが、私の結論は人や会社に「適度に無関心」になることです。
あの落合陽一さんも、自身のnoteで以下のようにおっしゃっています。
たくさん失敗しながら,その経験を糧にして自分しか見えないものを探し続けてはいる.だから自分は他人の失敗に寛容だし,あまり他人に興味がない.みんな違ってみんなどうでもいい,そんな世界になって欲しいと願っている.(それでもあなたは大切だ=社会的父性が必要なのは間違いがない)
働きづらさを助長する欲求不満ストレス
今でこそ転職は当たり前になり副業解禁も進んでいますが、生涯1企業で働く人はまだまだ多いです。そうなると、人生の幸福度は会社生活に大きく依存するため、仕事を通じて自己肯定感や承認欲求が満たされないとストレスがたまります。
高度経済成長期は年功序列エスカレーターに乗れていたことでストレスは中和されていました。また、スマホもSNSもなかったのでストレスを抱えている人の声も表面化していませんでした。ただ、経済成長が止まった今はストレスは中和されないどころか、SNSを通じて増幅し、多くの人の働きづらさを助長します。
複数のコミュニティに所属するメリット
会社生活への心理的依存度をさげるために、自身が所属するコミュニティを 複数もつことが解決策の一つです。 社会人向けのサークルやオンラインサロンもそうですし、会社の中で複数の役割を担ったり(兼務や複業)、ブログで情報発信をしたり、興味関心が合う人とSNSでつながるだけでもいい。今は多様なコミュニティの選択肢があります。
さらに、コミュニティごとに人格を変えてもいいし、複数選んでもいい。出入りも自由で、コミュニティが相互に干渉することもない。複数のコミュニティに所属することで、会社生活に対して「適度な無関心」が生まれ、心理的依存度をさげることができます。
「適度な無関心」を機能させるためのビジョン経営
働きづらさの解消には企業側の変化も必要です。必要なのは「適度な無関心」マネジメント。私が障害者雇用をする上で意識しているのは一歩引いて大目に見ること。それは決して野放しにするということではなく、「適度な無関心」で居心地の良い組織をつくった上で、「共感性の高いビジョン」で一体感を維持します。
多様性を活かす組織では、どこに同質性を置くかは非常に重要です。ここがしっかりデザインできれば、あとは多様な働き方や価値観を許容することで組織力は最大化されます。組織のリーダーは、同質性を生み出す「共感性の高いビジョン」を自分の言葉でしっかり語れなければなりません。
さいごに
これからの時代、従業員の満足度は「共感性の高いビジョン」と「適度な無関心」の2つが重要になってくるのではないでしょうか。これを実践できる企業が増えれば、発達障害者の活躍機会はもっと増えてくるはずです。