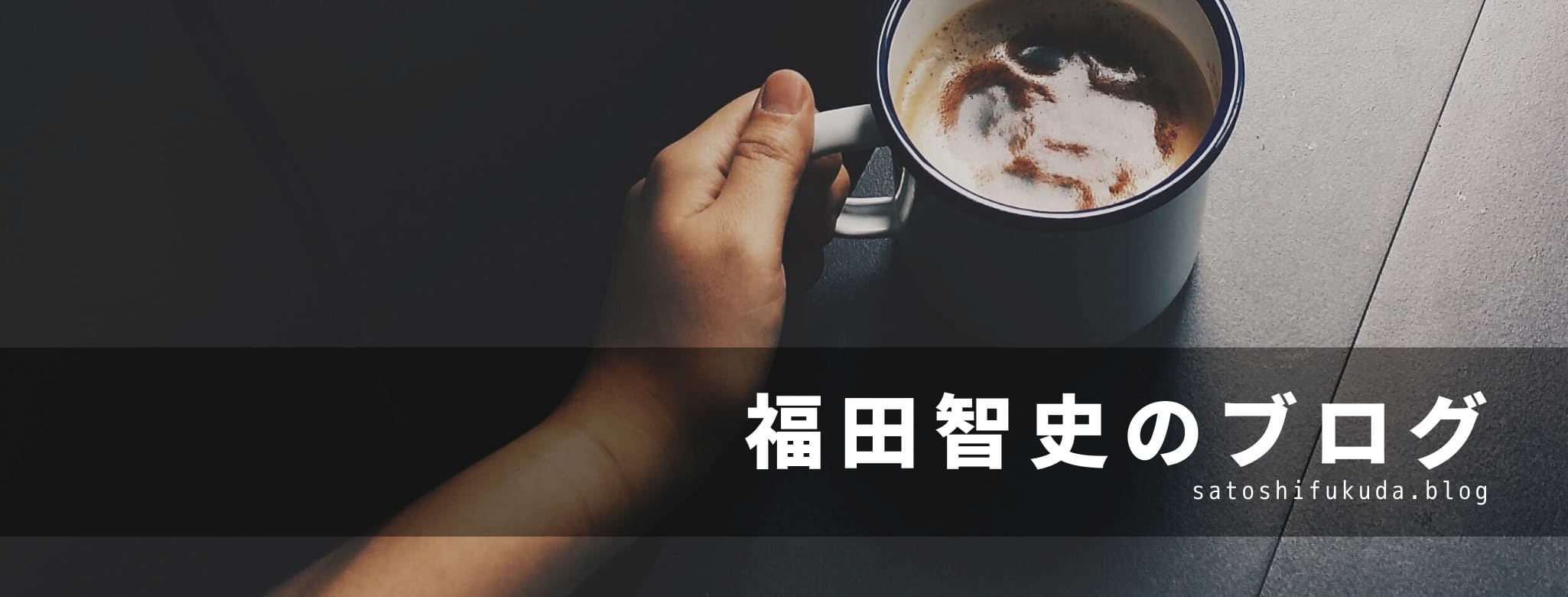日曜劇場「ドラゴン桜」と「発達障害」
はじめに
日曜劇場「ドラゴン桜」の最新話(第5話)がとても印象に残りました。原作漫画はシリーズ1から全話読んでいるんですが、ドラマにはオリジナルのシナリオ・キャラクターが存在します。第5話では、そのオリジナルキャラクターの一人として「発達障害の」生徒が登場し、模擬テストで高得点を叩き出します。
東京大学と発達障害
ドラマに登場する生徒は、聴覚情報はほぼ記憶に残らない(聴覚的短期記憶が弱い)その一方で、目で見た情報は確実に記憶できるという特性。ドラマの中では短期間に「辞書一冊記憶した」として物語が進みます。
聴覚情報が残らなければ大学で授業についていけないのでは…という不安がよぎりますが、東大では授業の音声を一字一句テキストにする「文字起こし文化」が盛んなので、東大には発達障害・ASDの生徒が多いとう事実がセリフになってました。
東大に入ればいいという単純な話ではない
もちろん東大にいけばすべてが解決するわけではありません。ドラゴン桜という漫画は「東大に行く」という原作のテーマ設定があるのでそういう見せ方になっていますが、発達障害者に限らず、人々が世の中に対して感じる理不尽や生きづらさに対して、桜木先生は以下のように言っています。
第1話で「世の中が気に入らないなら、勉強して、ルールを作る側に回れ」というセリフがありましたが、そこにもつながりますね。
そう思うならそういう世界をお前がつくればいい、社会を変えろ、常識を変えろ、研究者になればできるかもしれない。俺がお前を東大に入れてやる、そっから先は自分で考えろ。
最後には「自分で考える力」が大事なのも非常に共感します。
発達障害者の才能が開花された理由
こちらも、第5話のドラゴン桜に登場したセリフです。
世の中にはいろんな人がいる。多様性を尊重し、いろんな人と協調しあって生きていくことを生徒たちに学んでほしい。だから、発達障害の生徒も入学を希望するなら普通学級で受け入れてきた。
発達障害の生徒が才能を開花できたのは、この「勉強を強制されない自由な校風」があってこそ。 加えて「勉強は強制してはだめ、かと言って野放しにしてもダメ。人間には上を目指したいという本能があるから、その好奇心(向上心)を刺激してあげるのが教師の役目」とメッセージされていました。
印象に残ったこのセリフ。障がい者雇用にも通じるものがある気がします💡 「勉強は強制してはダメ、かと言って野放しにしてもダメ。人間が本能的にもってる好奇心を刺激すること、これが教師の役目」
— 福田智史 / Satoshi Fukuda🐌 (@satoshifkd) May 25, 2021
さいごに
金銭対価が発生する労働と勉強をひとくくりで語るのは違うかもしれませんが、今回の第5話は、「発達障害者を雇用し、戦力化する」ために大事なことも学べる内容でした。「自由な校風」と「好奇心の刺激」、この2つを発達障害者雇用の目的に沿って私の言葉に置き換えると「適度な無関心 と 共感性の高いビジョン 」です。
障害者雇用に取り組む企業で、この「自由な校風」と「好奇心を刺激する」を自分たちなりの言葉や表現で定義してみると、また新しい気付きがあるような気がします。テレビドラマなので少々過激なセリフ・演出もありましたが…それでもオススメです。 ドラゴン桜の第5話は、30日までTVerでも見れます!