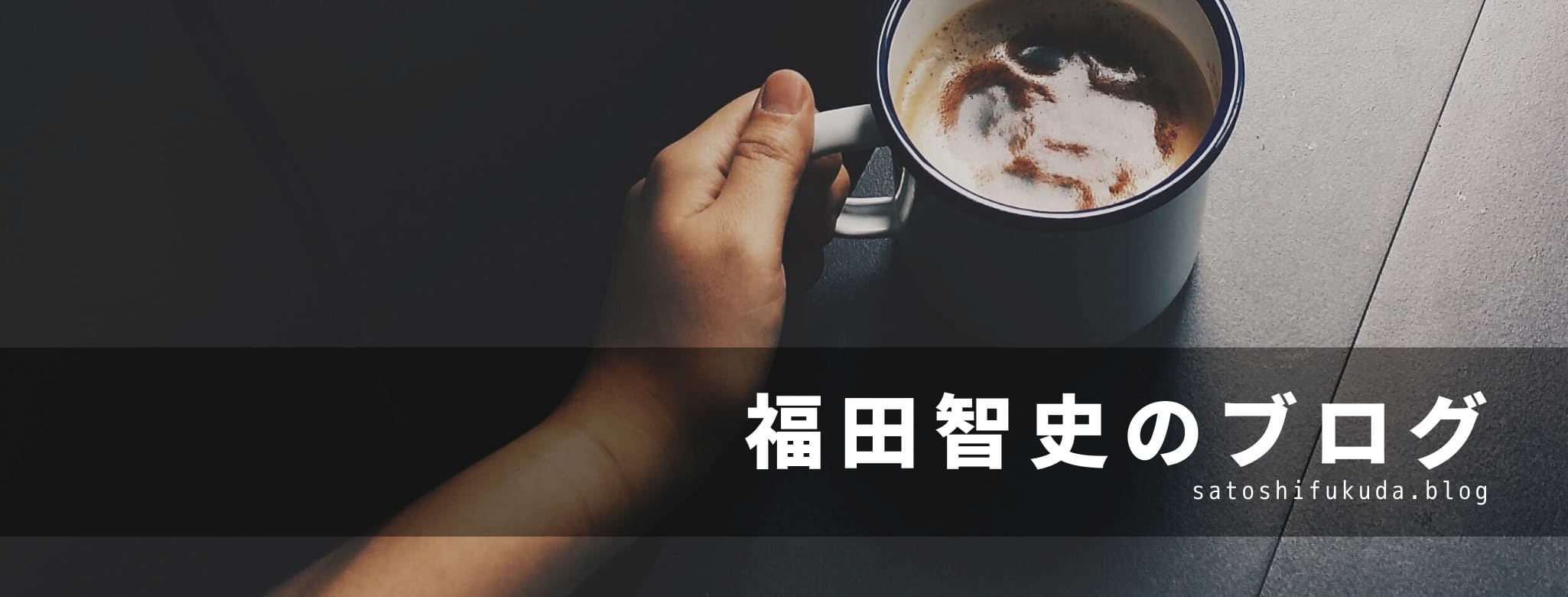「不登校は1日3分の働きかけで99%解決する」から学ぶ発達障害者のマネジメント
はじめに
スクールカウンセラーの先生の書いた「不登校は1日3分の働きかけで99%解決する」。不登校の原因は子供の心の発達不足と書かれています。
心の発達に必要なのは「親の愛情」と「承認欲求」の2つの栄養と言われていますが、社会人になると、親から愛情を注がれる機会は、幼少期のそれと比べて少ないです。そのため、発達障害者の雇用の現場では「承認欲求」を満たしてあげることをかなり意識してマネジメントをしており、そこには一定の効果があったと感じています。この本に書かれている「再登校に導く3つのポイント」に沿って、具体的にどんな事を意識していたかまとめました。
自信の水をつくる
障害者や子供に限らず「自信」は大事です。就職、転職、異動、転勤、昇進、降格、、、、社会に出ればさまざまな変化がありますが、こういった変化にアレルギー反応が出てしまう理由は「自信がないこと」です。社員に「自信を持ってもらう」事は、持続可能な障害者雇用には必要不可欠なんです。
褒める機会をつくる
持続可能な「自信」には成功体験が必要です。そして、その体験を第三者がしっかり褒めてあげることが大事。私が代表をしていた特例子会社では、社長である私が定期的に社員と 1 on 1 (個別面談)をする制度がありました。社員の悩みや不安を聞くだけでなく、社員の業務に対して「褒める」というポジティブなフィードバックをする機会としても機能させていました。

できるだけタイムリーに褒める
褒めるタイミングの理想は、できるだけリアルタイムに褒めてあげること。そうすることで「何が自信につながったか」を具体的に認識することができます。例えば、会議で良い発言や成果があった場合は、その場で、もしくは、会議が終わった直後にポジティブなフィードバックをしてあげます。
もう一つは毎日メールで出してもらっている業務日報です。一言二言でいいので、日報に返信をしてあげることで「見てくれている感」が伝わります。
自分の感情を付け加えて褒める
業務の成果に対して「褒める」だけでなく、自分の感情を付け加えて話すようにしていました。具体的には、「○○○さん、仕事のスピードあがったね。びっくりした!」とか「○○○さん、こんなこともできるようになったんだね。嬉しい!」こんな感じです。少し大袈裟くらいがちょうどいいです。
コンプリメント(”よさ” に気づかせる)
森田先生の本には、毎日3つ以上「よさ」を見つけて気づかせるべきと書いてあります。親子関係と違い、社員とは毎日会うわけではないので「毎日3つ以上」は難しいですが、「よさ」に気づかせるために意識してやっていたことがあります。
それは、過去の成果をもう一度褒めること。ちょっとした雑談の場でいいので、思い出したように「そういえば、こないだの○○○さんの仕事、あれよかったよね」こんな感じです。これも効果的です。
観察記録を付けることが大切
会社と家庭は違うので、育児手帳のように「観察記録を付ける」のは難しいですが、前述した「日報」を出させることでモニタリングが可能です。日報は本当におすすめです。
その日の成功や失敗を、書き手である社員が強制的に棚卸しする機会にもなります。社員が増えれば読む側も大変…という気持ちはわかりますが、Googleフォームなどを使えば、管理もかなり楽です。発達障害者を雇用する会社には是非とも導入してほしい仕組みです!
さいごに
誤解なきよう補足すると、不登校と発達障害に因果関係があるといった話ではありません。視点を変えれば、言語化が難しいと言われている発達障害者の雇用のヒントは色々なところから得られるということです。体系的に学ぶということがいかに重要か、この本に出会って再認識しました!