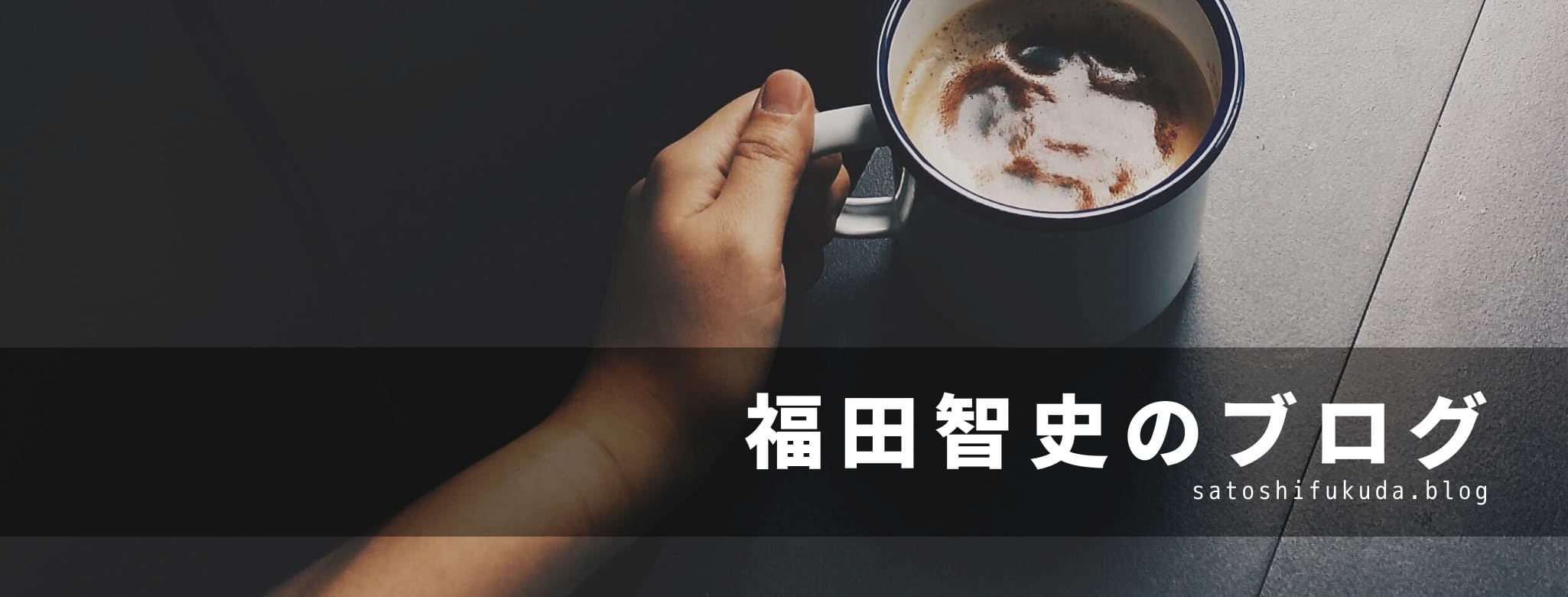障害者雇用に必要な組織づくりとは
はじめに
障害者を雇用するために「特例子会社の設立」や「障害者の採用」をするのは、それほど難しくありません。なぜなら、すでに多くの先行事例があるからです。一方、障害者で組織されたチームをどう継続的に運営していくかのノウハウはまだまだ少ないです。今回は、その「組織づくり」のポイントについて書いてみました。
企業ビジョンの設定
全社員が共感できるわかりやすいビジョンを
会社や組織に「ビジョンが必要だ」というのは語り尽くされていますが、それは、障害者雇用であっても同じです。名著「ビジョナリー・カンパニー」には、「時計をつくる経営者」という言葉がでてきます。トップ自らが指図して時刻を告げるのではなく、社員が自分で時刻を知ることができるように「時計をつくる」ことに注力するトップのことです。
「特例子会社だから」とか「障害者しかいない組織だから」とか、ビジョン不要の理由にはなりません。むしろ、健常者だけの組織よりも自走力で劣るため、全員が共感でき、そして自走力の源泉になるようなビジョンは絶対に必要です。ダイバーシティを機能させたいなら、「どこにユニバースを置くか」は必ずセットです。
どんなビジョンを設定すればいいか
私が代表をしていた特例子会社のビジョンは「障害者の能力が最大限に発揮でき、自律的に成長し続けられる会社をつくる」です。全社員に徹底して言い続けました。「この会社は、みんなの能力が最大限に発揮できて自律的に成長できる、そんな会社でありづつけるんだ」と。
もしビジョンの設定に悩んでいる方がいたら、ぜひ、そのまま使ってください!
オリジナルのキーワードや造語もありません。どんな業種にも適用できます。障害者が持てる能力を最大限に発揮できて成長できる場所をつくり、その人材を束ねて定量的な結果や実績につながるようにリードする。障害者を雇用するのであれば、この意識が重要です。
マネジメントの役割3つ
ビジョンをしっかり共有できたら、次にやることは3つです。
- 仕組みをつくる(人事制度などを設計する)
- 経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を確保する
- 仕事をもってくる(機会を提供する)
私が特例子会社の代表に就いてから取り組んできたことは、別途、詳細に記事にしてますのでぜひご覧ください。 本記事では「仕組みをつくる」の要点について触れておきます。

仕組みをつくる – ハード面はしっかりと
障害者が能力を発揮するための「合理的配慮」。これを実現するには、ある程度のお金と時間をかける必要があります。改正障害者雇用促進法でも「合理的配慮指針」というのははっきりと示されています。「具体的に何をしたらいいか」は、さまざまなところで紹介されているので情報には困りません。
- イヤーマフやサングラスの貸与
- デスクトップパーテーションの設置
- カウンセリングや保健師との定期面談制度
- 時間単位の有給休暇の取得
- 仮眠室の設置と仮眠休憩の取得(有給)
などなど。
私が特例子会社で取り組んだことも、後日、本ブログでまとめていく予定です!
仕組みをつくる – ソフト面は作り込みすぎない
できるだけ持続可能でるあることを目的にするならば、人事評価制度や福利厚生については「作り込みすぎない」ことが大事です。コストをかけて作り込めば短期的には確実に機能します。ただ、今は環境変化のスピードが早すぎるので維持コストが異常に高いんです。
新型コロナウィルスの感染拡大によりテレワークの導入が進んだことで、機能しなくなった人事制度や福利厚生はやまほどあります。まして、雇用ノウハウがないなかで進める「障害者雇用」ともなれば、管理する側や受注する仕事といった内的環境の変化も激しい。
ソフト面やるべきことは制度や福利厚生の作り込みではなく、冒頭に書いた抽象度の高いビジョンを徹底的に浸透させること。そして、1 on 1 をはじめとするマンツーマンのコミュニケーションにコストをかけることです。
さいごに
制度や仕組みで組織をマネジメントするには限界があります。障害者を戦力化するのであれば、仕組みに依存した効率化を求めるのではなく、ビジョンを掲げ、そして、個に向き合ってコミュニケーション量を増やしてみてください!