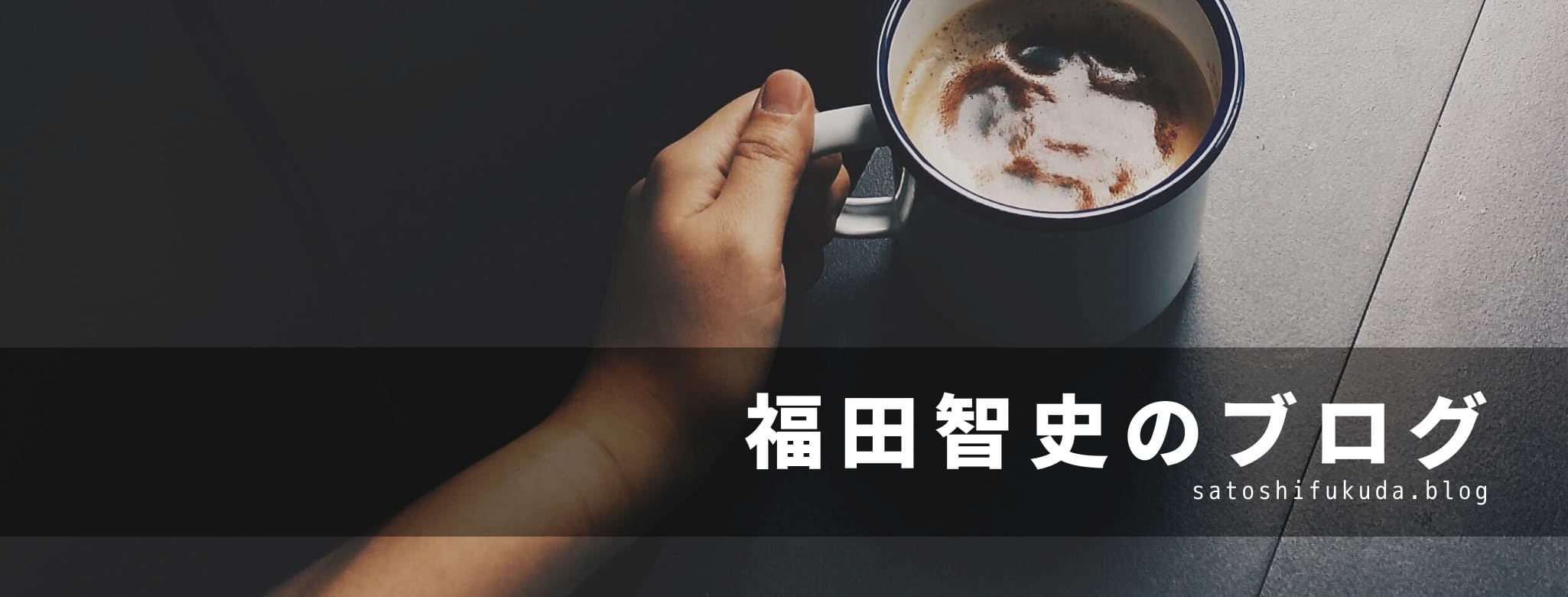障害者雇用から学んだ変化への第一歩力
はじめに
もうすぐ激動の2020年も終わります。年末になると「来年こそは!」といろいろ考えます。特に今年は、新型コロナウィルスの感染拡大によって大きな時代の転換期を迎えました。私はすでに40代..思わずこの本を手にとって読んでみたりもしました。
人間関係、習慣、考え方はは今のままでいいのか。テレワーク、フリーランス、副業など、10年前と比べて本当に選択肢は増えました。今こそ変わる時ではないか、そんなことをぼんやり考えてました。
現状維持こそが最大のリスク
「来年こそは!」と思っても、大きな一歩を踏み出せない人は多いです。私もその一人かもしれません。今ある安定を失いたくない、現状で特に不満はない、大きなリスクをとりたくない、、、そんな思いから変化を起こせないんです。変化の起こすにはエネルギーが必要です。原動力を自ら炊きたてて変化に飛び込める人はほんの一部の人かもしれません。
さらに、その変化を止めてしまうのが周囲の意見です。私たちが普段付き合ってる人の多くは「変化しない人」です。挑戦しようとする人を心から応援してはくれません。「現状維持こそが最大のリスク」とわかっていても、そんな環境も変化に対するブレーキになってしまいます。
働く障害者が持つ高い危機意識
私は、特例子会社グリービジネスオペレーションズ(以下、GBO)の代表をしていますが、そこで働く社員と定期的に 1 on 1 の面談をやっています。特例子会社での 1 on 1 については別の記事でも書いていますが、とにかく、1 on 1 からの学びが多いです。
GBOの社員の多くは発達障害で、学生時代や転職前の会社で大変な苦労をしています。就職活動ひとつとっても、健常者と比べ物にならないぐらい機会が少なく、就労を継続することも難しいとされています。だらこそ、うちの社員からは「現状維持こそが最大のリスク」に似た高い危機意識が伝わってきます。
逆境こそが変化の原動力
生まれ持った障害を「個性」でなく「逆境」と表現するのは不適切かもしれませんが、誤解を恐れずにいえば「自助努力でどうにもならない逆境」こそが危機意識の原動力なのだと思います。かくいう私もずっと大きな変化をできてません。ただ、もし明日会社を解雇されたら、明日年収が半分になったら、そんなどうにもならない強制力が働けば変化せずにはいられません。
私が特例子会社の代表に就いたときもそうでした。会社にとって必要な抜擢アサインだったので「逆境」とは思いませんでしたが、それでも、変化を強いられたことが「未経験も障害者雇用に取り組む」と思う原動力になりました。
さいごに
障害者をとりまく環境はどんどん変わっていきます。人材不足は慢性化し法定雇用率もあがります。テレワーク環境の整備によって働きやすい会社も増えてくるでしょう。一方、どんなに社会に選択肢が増えても、変化への「第一歩力」 が必要です。私は、そんな第一歩力を身につける術を、障害者雇用の現場から学んでいます。