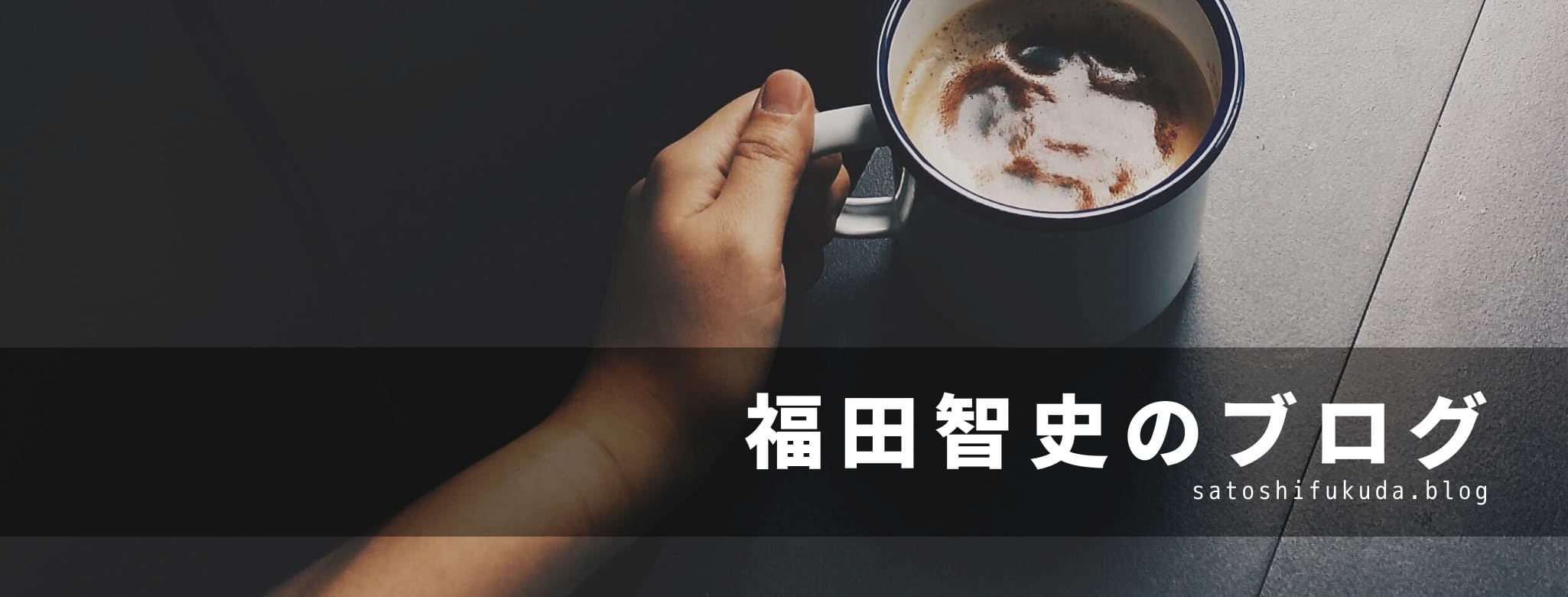特例子会社の社長奮闘記(5)
はじめに
障害者雇用の基礎知識がつき、自社の状況を理解したら、次は具体的な課題の抽出です。このプロセスで抽出された課題がこの後の経営アクションに直結するので、このプロセスはとても重要です。第5回の本記事では「特例子会社で働く社員の課題抽出」について書きたいと思います。
- 経営目標の設定(定量目標や企業ビジョン)
- 障害者雇用の基礎知識や他社の先行事例を把握
- 特例子会社についての現状把握(オフィス環境や人事制度、福利厚生等)
- 特例子会社で働く社員の現状把握
- 特例子会社で働く社員の課題抽出
- 特例子会社に仕事を発注してくれる本社及びグループ子会社の現状把握
- 特例子会社に仕事を発注してくれる本社及びグループ子会社の課題抽出
- 特例子会社の改善(合理的配慮の強化、社内制度の充実、採用、人材育成など)
- 改善された特例子会社のプロモーション(業務の受注拡大)
このシリーズを初めてみるという方は以下の記事を先にご覧いただくことをオススメします!

過去記事の一覧はこちらから。

課題抽出の観点と分類方法
一口に課題抽出といっても、ブレスト的に大量に書き出しても次のアクションに繋がりません。どういった観点(基準)を持ってそれを課題と認定するのか、その方針を決めておくことが重要です。そこで登場するのが第1回の記事でも書いた「企業ビジョン」。迷ったときの道標になってくれます。
私が代表をしていた特例子会社グリービジネスオペレーションズ(以下、GBO)の企業ビジョンは「能力を最大限発揮でき、仕事を通じ自律的に成長できる会社をつくる」。私の場合は、このビジョンに沿う形で以下の2つに分類して課題抽出を行いました。
- 能力発揮の妨げになっている課題
- 自律的成長の妨げになっている課題
能力発揮の妨げになっている課題
障害特性によって自身の能力を十分に発揮できてない社員に向けた合理的配慮、それが「能力の妨げになっている課題」の解決です。
私が代表に就任した当時、発達障害者向けの配慮実績は国内に事例が少なく、そもそも目に見えづらい障害であるため、当事者である社員への直接ヒアリングからヒントを得ました。その内容をあげれば枚挙にいとまがないのですが、GBOで抽出された課題をいくつかご紹介します!
物理的なもの
- 電話やチャットツールでの連絡はマルチタスクを強いられるので苦手
- 納期の短い仕事は締め切りが気になって業務に集中できない
- ちょっとした物音や人の動きが気になって業務に集中できない
- 角の席(背後が壁)じゃないと業務に集中できない
- 作業をわかりやすく手順書にして見える可しないと着手できない
- 一つのパソコンの画面でウィンドウを切り替えながら作業するのが苦手
- 易疲労性(過度に疲れやすい)があるので仮眠をさせてほしい
- ずっと座ったままでは集中して作業ができない
- アナログ時計では時間がすぐに把握できない、デジタル時計では時間の感覚がわかない
精神的なもの
- 仕事以外のこと(家庭や友人関係)の悩みが頭から離れない
- 業務で困ったときや質問があるときに、なかなか聞きに行けない
- 上司(健常者スタッフ)が、自分の障害特性に理解があるのかわからない
- 自分は会社に必要とされているのか、役に立っているのか不安になる
- 会社の人と仕事以外でほとんど話したことがないので、居場所がないように感じる
- 何度も同じミスをしてしまうので、自分はもうダメなんじゃないかと自信がもてない
自律的成長の妨げになっている課題
会社で働くという事は、能力を発揮して目の前の業務を消化するだけでありません。その能力を日々進化させ、成長していく必要があります。もちろん、成長のスピードや歩幅は人それぞれですが、その成長を本人が実感できているかが重要。
成長こそが「やりがい」や「非金銭的なリターン」となり、社員の離職率の低下にもつながります。GBOで過去に抽出された「自律的成長の妨げになっている課題」をいくつかご紹介します!
- がんばって成果を出したが、あまりそれを実感できていない
- 「成長したね」と言われても、どう成長したか自身で理解できていない
- 成長意欲を維持するために、わかりやすい目標が欲しい
- 業務時間外で、勉強したりスキルアプする機会が欲しい
- 興味分野に詳しい人に直接教えてもらえたり研修してもらう機会がない
- もっとグリーグループの本業に近いところで仕事をしてみたい
さいごに
あらためて言語化してみると、多くの健常者にとっても共感できる課題が多いです。発達障害者にとって働きやすい環境というぼは、誰にとっても働きやすく、そういった多様性に富んだ労働環境こそが、企業の競争力の土台となるのではないでしょうか。(次の記事を見る)