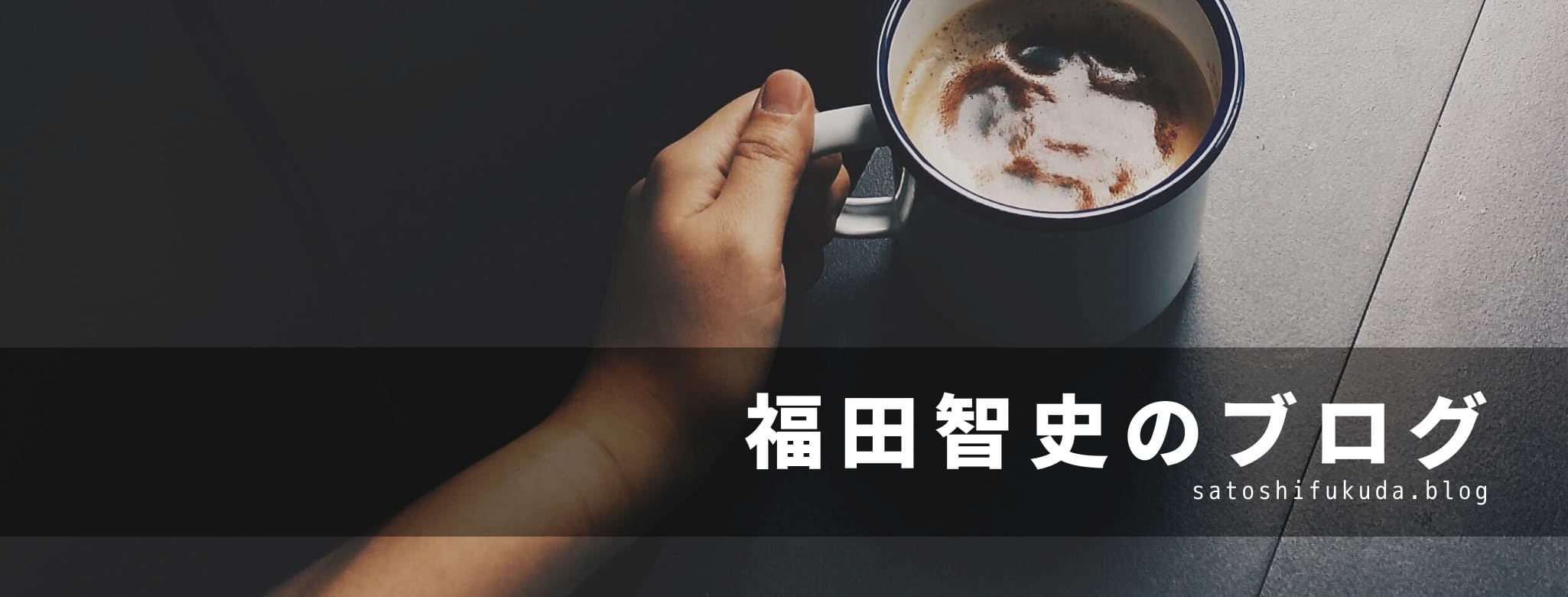特例子会社の社長奮闘記(4)
はじめに
いよいよ、当事者である社員と本格的に向き合います。第4回の本記事では「特例子会社で働く社員の現状把握」について書きたいと思います。
- 経営目標の設定(定量目標や企業ビジョン)
- 障害者雇用の基礎知識や他社の先行事例を把握
- 特例子会社についての現状把握(オフィス環境や人事制度、福利厚生等)
- 特例子会社で働く社員の現状把握
- 特例子会社で働く社員の課題抽出
- 特例子会社に仕事を発注してくれる本社及びグループ子会社の現状把握
- 特例子会社に仕事を発注してくれる本社及びグループ子会社の課題抽出
- 特例子会社の改善(合理的配慮の強化、社内制度の充実、採用、人材育成など)
- 改善された特例子会社のプロモーション(業務の受注拡大)
このシリーズを初めてみるという方は以下の記事を先にご覧いただくことをオススメします!

過去記事の一覧はこちらから。

特例子会社で働く社員の現状把握( 1 on 1 )
社員の現状を把握するためにオススメの方法は 1 on 1 です。つきなみではありますが、やはり対面でコミュニケーションをとるのが一番です。
社員が多ければかなり時間をとられるので「非効率」に思えるかもしれませんし、かく言う私も、特例子会社の代表就任当時はそう思ってました。ただ、外見では特性がわかりづらい発達障害については、本人と直接話すしかないというのが私の結論です。
基礎知識も有効ですが、その上で、個々に向き合えば向き合うほど「適材適所」について考えさせられます。私自身も、障害者も健常者も関係なく、
- 人によって持っている能力は違う
- 人によって持っている能力が十分に発揮される環境も違う
- 人によって持っている能力が十分に発揮される環境は年月の経過と共に変化する
ということを学びました。
文字にしてみれば当たり前のことなのですが、新卒一括採用から定年退職まで、終身雇用を前提とした日本的雇用システムが色濃く残る現代日本においては、根本的に「個に向き合う」というマネジメント慣習がありません。障害者雇用に関わり始めた当時の私もそうでした。
障害者の働きづらさや生きづらさの根底には、高度経済成長期に醸成された日本社会の画一的・集団主義的な価値観があると気付いたことは、私のその後の人生においても大きなターニングポイントになったと思います。1 on 1 を、常設制度化して継続すると決めたのもこの頃です。
また、時間の経過とともに、1 on 1 の目的も徐々に変化させていきました。詳しくは以下の過去記事もぜひご覧ください!

特例子会社で働く社員の現状把握(日報)
1 on 1 ともう一つオススメなのが「日報」の提出です。1 on 1 と違い、より短期のスパンで社員の声を拾えるようにしておきます。メールやGoogleフォームを使うことで蓄積性と検索性も担保されます。よく「継続的に 1 on1 やってたら話のネタが尽きませんか?」と聞かれるのですが、日報があるとその課題も解決します。
私の場合、社員との 1 on 1 の前には必ず対象者の日報をチェックして、そこから会話をはじめていました。この手のレポーティングは得てして形骸化しやすいのですが、 1 on 1 と組み合わせることで、私だけでなく社員にとってもその意義が明確になるんですよね。
さいごに
当事者である社員のことを知ろうとする時、もっとも大切なことは「個人と向き合う意識」を持つことです。どんなに忙しくても一括(ひとくくり)で見てはいけません。発達障害といってもその特性は千差万別です。しっかり時間をとって、個々の特性を正確に把握することが大事です。(次の記事を見る)