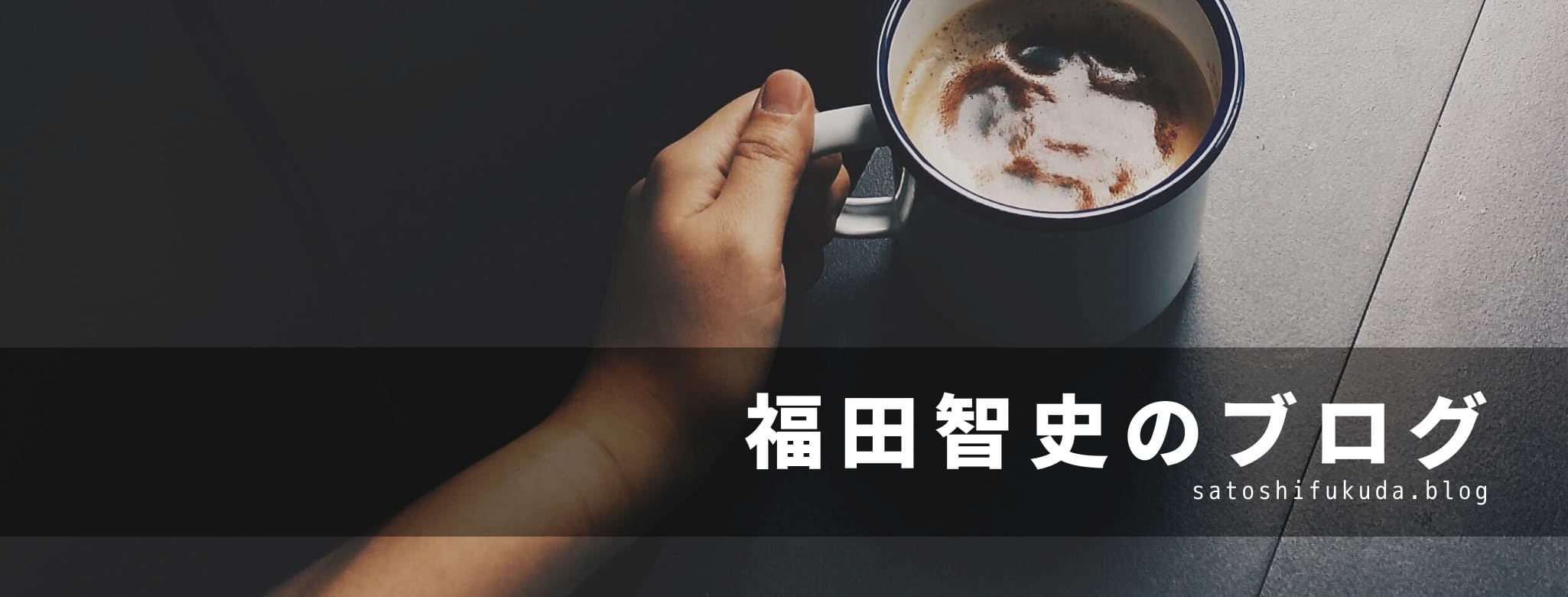「小学生の子が勉強にハマる方法」から学ぶ発達障害者のマネジメント
はじめに
中学受験専門の塾「伸学会」の先生が書いた本「『やる気』を科学的に分析してわかった小学生の子が勉強にハマる方法 」。科学的に実証された勉強を楽しむ「技術」について述べられています。この本で紹介されていた「6つのやる気エンジン」から、発達障害者のマネジメントに役立つヒントを考えてみます。
6つのやる気エンジン
報酬志向
報酬を得るために勉強するというのが「報酬志向」。本の中では「最初は、この『ご褒美作戦』から入ると効果的」と書かれています。私が代表をしていた特例子会社グリービジネスオペレーションズ(以下、GBO)では、これに近い仕組みとして「MVP表彰制度」を設けていました。
MVPとは「金銭的ボーナス」ではなく「イベント」です。GBOの場合は、社員と管理スタッフの投票を参考に「その年に企業ビジョンをもっとも体現した人」を選定し、全社員の前で表彰していました。これも1つの「ご褒美」であり「自己肯定感ボーナス」です。その様子は過去記事でも紹介しています!

昇給や賞与、正社員登用といった経済的価値のある「ご褒美」も存在しました。ただ、より持続可能な報酬制度としてMVPや皆勤賞は効果的に機能していたと思います!
自尊志向
人に勝ちたい、負けたくない、置いていかれたくない、という気持ちで勉強するのが「自尊志向」。本の中では「競争で生徒を煽る戦略は使いやすいが、少ない勝者に対して敗者が多くなってしまい全体のやる気につながりにくい」と書いてあり、それを解決するための工夫も書かれています。
報酬志向でも紹介した「MVP制度」は、自尊志向の刺激にも効果的です。給与や賞与といった金銭報酬は、対象者だけに内密に伝えられるものですが、MVPは全社員の前で大々的に発表されます。そのため、MVPを受賞できなかった社員に「次こそは自分も獲りたい」という競争心が生まれます。
一方、「MVP表彰制度」は諸刃の剣でもあります。うまく運用をしないと一部の社員のモチベーションの低下を招いてしまいます。そこで重要なのは一定の「透明性」です。GBOでは、
- MVPの選定基準を企業ビジョンに一本化する
- 経営陣の意思だけでなく、社員の意見を参考にする
というルールがありました。基準を企業ビジョン(企業理念)に一本化することで継続性と公平さが確保され、ビジョンの浸透も促進されます。また全社員から「他薦を募る」ことも透明性の確保につながります。
関係志向
他者につられて勉強するのが「関係志向」。本の中では「やる気は感染します。高い意欲を持った子の周りには、意欲の高い子が集まります。仲のいい友達グループで勉強するとやる気が出る」と書かれています。やる気は「感染する」という表現が好きです。
新型コロナウィルスの感染拡大以降、在宅ワークが広がったことで関係志向を刺激するのが難しくなりました。在宅ワーク環境では「同僚が何をしているか」が見えづらく、組織としての一体感も薄まります。GBOでは「つながり感」を保つためにeスポーツの活用なども試みました。

一方、発達障害者は、感覚過敏や易疲労性を抱える人も多く、マルチタスクも得意ではありません。合理的配慮上は「テレワーク」は有効な手段にもなります。無理に「関係志向」を刺激せずとも、マイペースで仕事ができることを優先してもいいでしょう。
実用志向
仕事や生活に活かすために勉強するのが「実用志向」。本の中では「授業内容がどのように生活や社会で役立っているかを知ることは、大きな意味があります」と書かれています。仕事においては、まさにこの実用志向が「働きがい」に直結します。
GBOの親会社は上場企業です。そのため、グループの経営状況や事業進捗は「決算報告」として四半期ごとに一般公開されます。私が代表をしていたとき、公開された決算資料を用い、毎四半期ごとに全社員向けに「決算説明会」を開催していました。
ただ資料を朗読するのではなく、決算資料に掲載されている事業と、GBOで受託している業務のつながりを丁寧に説明します。これにより、普段やっている業務が「会社に貢献している」「世の中に大きな影響を与えている」実感がわきます。これがまさに「実用志向」です。
訓練志向
知力を鍛えるために勉強するのが「訓練志向」。本の中では「勉強を続けていくと、『前はできなかったことができるようになった』という実感を得られるタイミングが来ます」と書かれています。他社との比較でなく自己比較ですね。
発達障害者のマネジメントに 1 on 1 が有効であるという記事の中で「目的が変化してきている」と書きましたが、まさにそれは「訓練志向」を刺激するためです。他人を見るのではなく、自分自身の成長(変化)を言葉にしながら上長が社員と「一緒に振り返る」ことが大事です。
人の学びは「自分の経験からが7割」「他者の話しからが2割」「研修や書籍からが1割」であり、その自分の経験を振り返るのが 1 on 1

充実志向
学習自体が楽しくなるのが「充実志向」。ここまできたら理想的ですね。周りから余計な刺激を与えなくてもどんどん自走していきます。仕事においてこの状態に到達するのは難易度が高いですが、こういったステップを踏むことで徐々に「充実志向」に近づいていくと思います。
- 第一段階:報酬志向、自尊志向(外発的動機付け)
- 第二段階:実用志向、訓練志向(内発的動機付け)
- 最終段階:充実志向(無の境地)
さいごに
発達障害者のマネジメントに有効な制度や仕組みはさまざまありますが、「小学生の子が勉強にハマる方法」の観点でグルーピングしてみました(関係志向は除外)。
| 第一段階 | 第二段階 | 最終段階 | |
| 報酬志向、自尊志向(外発的動機付け) | 実用志向、訓練志向(内発的動機付け) | 充実志向 | |
| MVP表彰制度 | 決算説明会 | 1 on 1 (目的変化) | |
制度や仕組みは一斉に導入するものではありません。一朝一夕に効果が出るものでもありません。本記事の内容は「何をどんな順番で導入するのか」の参考になるのではないかと思います。