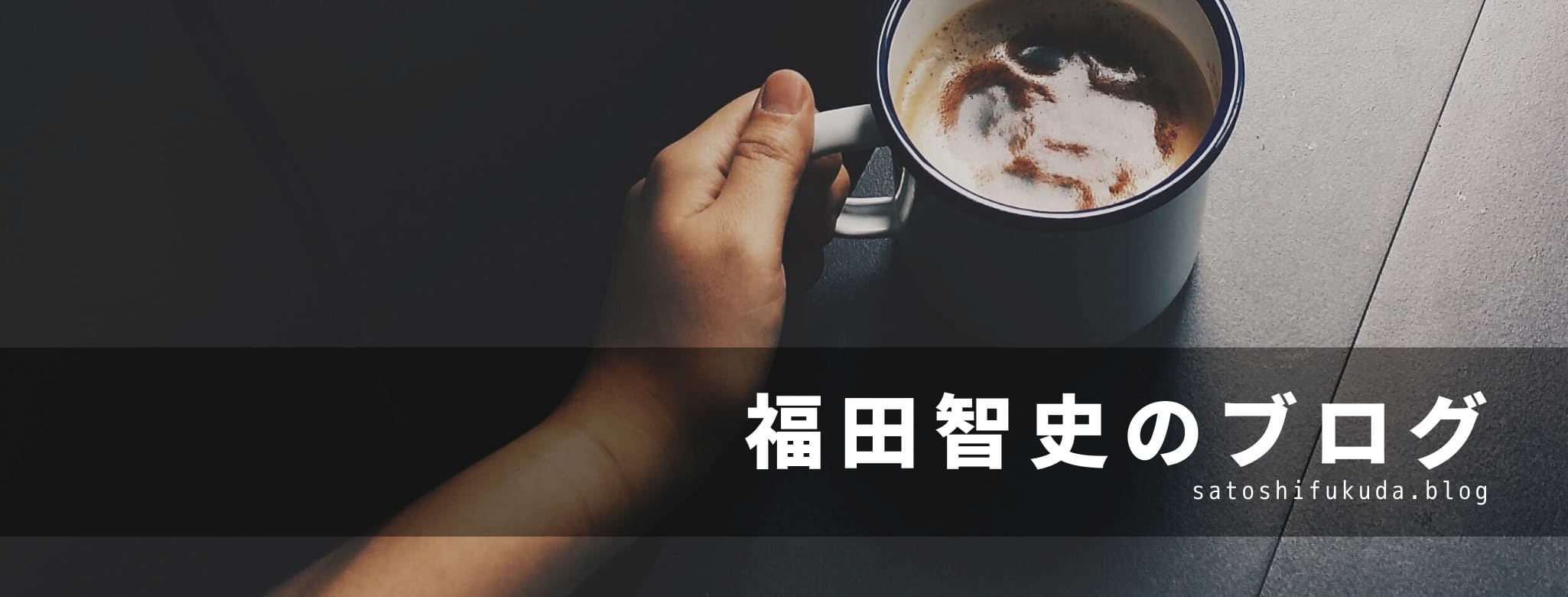特例子会社のメリットとは – 経営の現場から
はじめに
障害者を雇用する手段としての特例子会社。金融商品取引法における「特定子会社」と混同されることがよくありますが「特例子会社」です。
特例子会社(とくれいこがいしゃ)とは、日本法上の概念で、障害者の雇用に特別な配慮をし、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条の規定により、一定の要件を満たした上で厚生労働大臣の認可を受けて、障害者雇用率の算定において親会社の一事業所と見なされる子会社である。完全子会社の場合が多いが、地元自治体の出資を入れる第三セクターの形を採るものもある。 – Wikipediaより
特例子会社のメリット・デメリットについては様々な意見があります。ほんの一例ですが、こちらの「特例子会社のメリット・デメリット」で書かれている特例子会社のデメリットには違和感を感じました。
デメリットの存在は否定しませんが、「特例子会社だからこうだ」という固定観念は非常に危ない。多くの障害者にとって働き方の選択肢を狭めてしまいます。中には「特例子会社は障害者を差別するための手段だ」という過激な意見も見かけます。
企業も人も色々であるように、特例子会社にも色々あります。特例子会社の代表を5年以上務める私が、経営の現場からみたメリット・デメリットについて書きたいと思います。
特例子会社のメリット
独立した子会社であることが最大のメリット
特例子会社で障害者を雇用するメリットは大きく2点。
- 独自の環境や制度を整備しやすい
- 情報の共有や意思決定が迅速
特例子会社であるグリービジネスオペレーションズ(以下、GBO)では、特例子会社の形をとらなければ、発達障害者が働きやすい環境はスピーディーにつくれませんでした。正社員の登用制度の整備も難しかったと思います。
子会社であることで採用の意思決定スピードがあがり、40名超の発達障害者を雇用することができています。 人事制度や就業規則、研修なども、本社とほぼ変わりません。時間単位の有給休暇や、業務中に給与控除なしで使える仮眠室など、本社より配慮の進んだ環境を構築できています。これも子会社であることのメリットです。
特例子会社を活用して「働く」機会をつくる
特例子会社を「健常者と障害者を区別していて良くない」とか「本来は同じ職場で働ける社会であるべき」と否定する意見があるのも事実です。反論するわけではないですが、特例子会社であることのメリットが軽視されている気がします。そもそも、そのメリットは現場の人間でないとわからない。
子会社として独立させることで障害者への配慮環境が圧倒的に作りやすい。差別をなくしたいという理想はよくわかりますが、配慮のある環境で能力を十分に発揮して「働く」ことが一丁目一番地。できることから始めていかないといつまでたっても社会は変わりません。
特例子会社の活用で生み出されるコストメリット
多くの企業でアウトソーシングが活用されていますが、そこには見える化されてないないコストが存在します。合見積から社内稟議の承認、NDAや基本契約などの契約処理、発注から検収、請求書処理、セキュリティ制限などなど…。
これらのオペレーションコストは、特例子会社のような100%グループ内企業との取り引きにおいては大幅にカットすることができます。障害者雇用を担う側がいかにして経済合理性を証明できるか。企業の障害者雇用を推進するにはこういった観点やスキルもとても大事になってきます。
特例子会社のデメリット
次に特例子会社のデメリットです。特例子会社の立ち上げにはそれなりのコスト(初期投資)がかかります。特例子会社の存在にデメリットがあるというよりかは、そもそも、特例子会社を立ち上げて軌道にのせるのが難しいというのがポイントです。ハードルは大きく2点。
- 特例子会社を運営する人材の選定が難しい
- 特例子会社の活用をグループ全体で取り組む必要がある
この2点をクリアできれば、特例子会社のデメリットはそこまで顕在化しません。よく言われている「単純作業しかない」とか「社会から取り残される」といったデメリットは感じなくなるはずです。
さいごに
私自身、引き続き多くの企業が障害者雇用に積極的に取り組めるよう、特例子会社のメリットや配慮環境を作るためのノウハウの発信は続けていきます。「特例子会社がよくない」という固定観念がなくなり、障害者にとって有用な選択肢の一つになれるよう、これからも多くの企業様と一緒に努力していきます。
人事経験ゼロの私がどのように障害者雇用に取り組んだかは、別の記事でまとめています。ご興味ある方はぜひご覧ください!