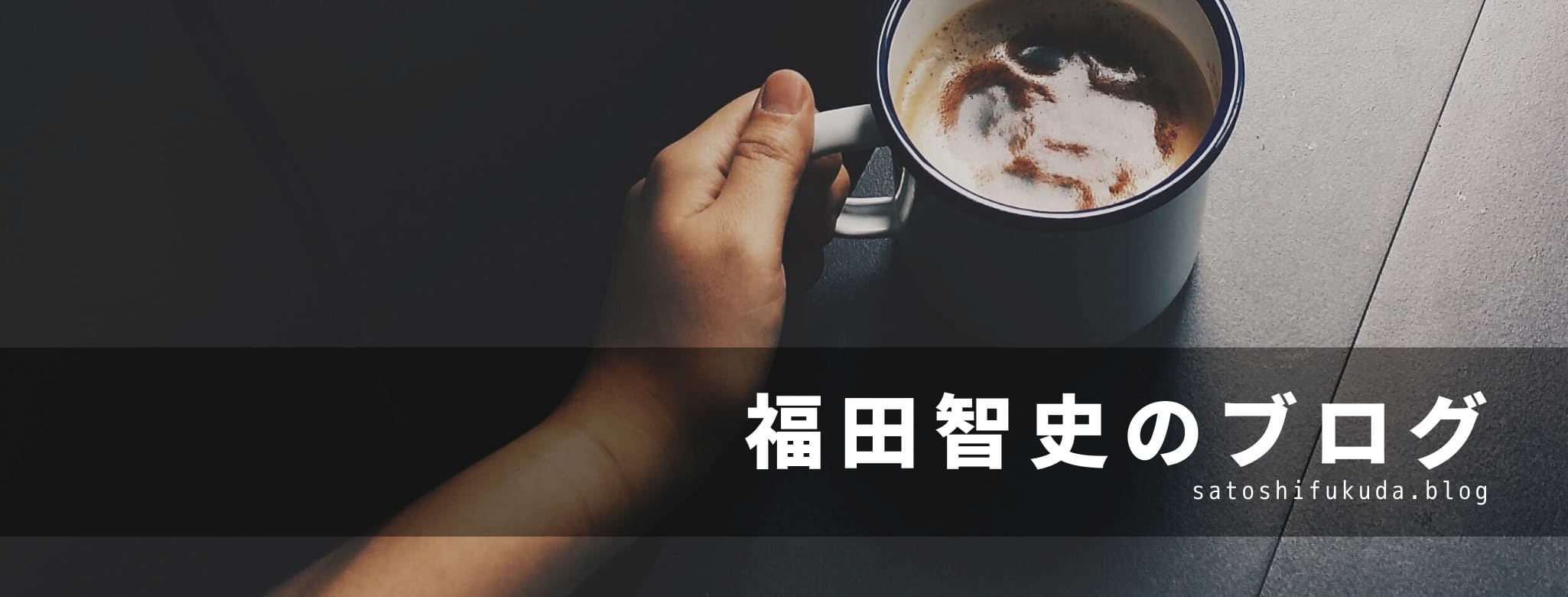特例子会社の社長奮闘記(2)
はじめに
第2回の本記事では「障害者雇用の基礎知識や他社の先行事例を把握」について書きたいと思います。
- 経営目標の設定(定量目標や企業ビジョン)
- 障害者雇用の基礎知識や他社の先行事例を把握
- 特例子会社についての現状把握(オフィス環境や人事制度、福利厚生等)
- 特例子会社で働く社員の現状把握
- 特例子会社で働く社員の課題抽出
- 特例子会社に仕事を発注してくれる本社及びグループ子会社の現状把握
- 特例子会社に仕事を発注してくれる本社及びグループ子会社の課題抽出
- 特例子会社の改善(合理的配慮の強化、社内制度の充実、採用、人材育成など)
- 改善された特例子会社のプロモーション(業務の受注拡大)
このシリーズを初めてみるという方は以下の記事を先にご覧いただくことをオススメします!

過去記事の一覧はこちらから。

障害者雇用の基礎知識の習得
経営目標を設定した次は実務です。とはいえ初めての障害者雇用。コンプライアンスの観点でも基礎知識の習得は必須でした。書籍や民間企業が主催する有料のセミナーなどもありますが、一番のオススメは行政機関や公益団体が実施している講習に参加すること。今回は私が実際に受講した講習を2つご紹介します!
障害者職業生活相談員資格認定講習 ※無料
まず最初に足を運んだのは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が主催している「障害者職業生活相談員資格認定講習」。代表をしていた特例子会社では、健常者の管理スタッフは必ずこの講習を受講し、障害者職業生活相談員の認定を受けてました。
障害者の雇用の促進等に関する法律では、障害者を 5 人以上雇用する事業所には、障害者の職業生活全般にわたる相談・指導を行うため、「障害者職業生活相談員」の資格を有する者のうちから、当該相談員を選任し、所轄の公共職業安定所に選任届けを提出することが義務づけられています。
個人では申し込めない等、受講には一定の条件はありますが、受講もテキストも無料! 詳しくは以下の公式サイトで確認してください。初めて障害者雇用に関わる皆様、まずはここからです。

雇用環境整備士第Ⅱ種(障害者雇用)認定講習会 ※有料
過去、以下の記事で企業向けの「雇用環境整備適正事業者認定制度」をご紹介しましたが、同じ一般社団法人日本雇用環境整備機構が提供している個人向けの認定制度が「雇用環境整備士」です。

私が雇用環境整備士資格講習を受けたのは2018年。代表に就いたのが2013年の12月なので、だいぶ時間が経過してからでした。有料ではありますが、忘れかけていた障害者雇用促進法の内容をおさらいでき、テキストも充実した内容だったので「これは受講してよかった!」と思いました。これから障害者雇用に取り組む方だけでなく、基本的な知識を復習したい方にもオススメです。
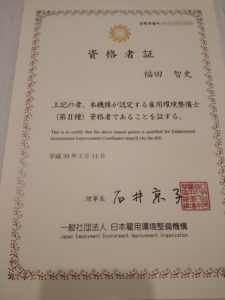
雇用環境整備士になるには、本機構の定める講習会を修了または本機構の定める資格試験に合格し、育児者・障がい者・エイジレス等の対象者の公平な雇用機会促進に努めるための法律・実務に関する知識を有する者と認定された場合に資格者証が付与されます。 – 公式HPより
他社の先行事例を把握
障害者雇用に関する基礎知識を習得したあとは、障害者雇用に取り組まれている先人の皆様にお話を聞きに行きました。はじめての障害者雇用、教科書を読んだだけでうまくいくなら苦労しません。多くの試行錯誤を繰り返し、実績を積んでいる企業から学ぶことは多いです。
必ず聞く質問として用意していったものは以下の5つ。
- 社員数と働いている社員の障害特性の内訳
- 管理スタッフ(健常者)の数とアサイン経緯
- 障害者の採用方法と採用で見ているポイント
- 障害者の就労定着のための合理的配慮の内容
- 業務の切り出し方法と業務の内容
20〜30社は訪問させてもらいましたが、無駄足は1社もなく、漏れなく価値ある面会でした。前述の講習で学んだこととは違い、より実践的で生きた学びがあります。障害者雇用は、その支援を生業にしているコンサルタントや民間企業もありますが、実際に雇用している企業の話しを聞くのがもっとも参考になります。
どうやって面会を取り付けたか。
- SNSを通じて障害者雇用に取り組んでいる友人・知人に直接コンタクトする
- 「特例子会社」と検索してヒットした企業のホームページから問い合わせをする
この2つです。アナログです。 全ての企業が訪問・見学を受け入れてくれた訳ではありませんが、それでも半数以上の企業が快く受け入れてくれました。また、早期に障害者雇用界隈の企業ネットワークを構築できたことで、継続的に情報交換をしたり、まだ見ぬトラブルに見舞われたときにアドバイスをもらうこともできました。
発達障害について知る
代表をしていた特例子会社は、社員の70%以上が発達障害者でした。そのため「発達障害」に特化して知識を深める必要がありました。「発達障害」についても、さまざまな学びのソースがありますが、個人的におすすめの「わかりやすい」情報ソースを以下の記事にまとめています。ご興味ある方はぜひご覧ください。

さいごに
本記事の内容は、現場に入る前の最低限の「準備」になります。会社のトップともなると、自身の価値観や能力だけで物事を進めてしまいがちですが、会社の器は社長の器以上に大きくなりません。井の中の蛙にならぬよう体系的に学ぶことは重要です。(次の記事を見る)